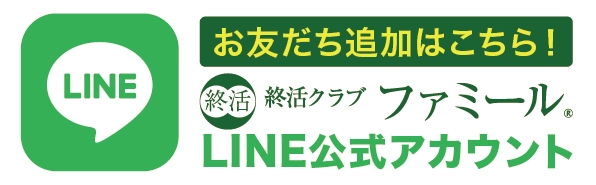- Home
- 葬儀と終活の豆知識
葬儀と終活の豆知識
埼玉県熊谷市の終活|近年、急増中の葬儀・死後の「生前契約」とは?そのメリットと注意点

生前契約は、残された家族にもとてもメリットがあり、検討する価値があります。今回は、生前契約のメリットや配慮しておきたいことと、安心して任せられる生前契約についてご紹介します。
目次
生前契約とは

葬儀の生前契約とは、残された家族に負担をかけるのを避けるために、自身の葬儀の生前契約をすること。
葬儀を行うということは、家族には金銭的負担のほか、傷心のなか慌ただしく葬儀の手配を進めなければいけないという心身的負担もかけることになります。生前契約は、家族にこのような負担をかけたくない場合や、ご自身が望む葬儀にしたい場合などにオススメの終活です。
生前契約はお一人様の終活に大人気
生前契約がお一人様の終活に注目されている理由は、自分の思いを託すことができることにあります。
高齢者で一人暮らしの方の場合、終活を行おうとしても、後を託せる人がいないこともあります。亡くなったあとのことを考えると、葬儀や住んでいる場所の整理など、誰が行うのか不安に思うこともあるでしょう。
そんなときに役に立つのが生前契約です。一人暮らしで身寄りがない場合でも、生前契約をしておくことで、亡くなったあとの整理や、自分の思いなどを託すことができるため、注目されています。
家族の代わりにサポートしてくれる生前事務委任契約とは?
生前事務委任契約とは、家族が行うような生活上での支援や、自分の財産の管理などを家族に代わって行うもの。
似たようなものでは、任意後見や法定後見がありますが、これらは対象者の判断能力が衰えてからのスタートとなります。生前事務委任契約の場合は、判断能力もしっかりしており、元気なうちから契約が行えるのが特徴です。
生前事務の内容には病気の場合の医師からの説明、手術の立ち会いや、アパートや老人ホームなどへ入居する際の身元保証人となること、財産の維持管理などがあります。
高齢者の中には、判断能力は十分にあるが、体が不自由で出歩くことが難しく、銀行に行って財産の管理を行うことができない方もいます。家族や身寄りがいればフォローしてもらうことも可能ですが、身寄りがない一人暮らしの場合はどうすることもできません。そんなときに、サポートをしてくれるのが、生前事務委任契約です。
亡くなった後に必要な処理をしてくれる死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、契約者が亡くなったあとに必要な処理をしてくれる契約のことを指します。人が亡くなったあとに行う必要のある処理を「死後事務」と呼びます。人が亡くなったあとは、さまざまな処理が必要となってきます。
死後事務契約の内容には、公共料金の支払いや整理、住居の片付けや、契約者の葬儀や永代供養、保険や年金の手続きなどがあります。
生前契約のメリット
落ち着いて葬儀について考えることができる
生前契約を検討することで、元気な時にじっくりと考えることができます。葬儀についての希望は、エンディングノートに書き留めておくことで、家族に伝えることもできます。
家族の負担を減らすことができる
生前契約では、葬儀にかかる費用を事前に把握しておくことができます。費用をあらかじめ支払っておくことで、葬儀を執り行う家族の負担を軽減することもできます。
生前契約を考える時に配慮しておきたいこと
生前に葬儀の契約をするというのは、これまであまりなかったことです。縁起が悪い、葬儀内容に納得がいかないと感じる親族の反対意見があるかもしれません。その為、家族に相談しながら進めることが大切です。
生前契約に係る5つの書類

生前契約では、医療上で判断を行う際の意思表示の代理や、財産の管理などの重要な部分も担っています。特に重要な事柄である場合、書類をもって契約が行われます。
①財産管理委任契約書
財産管理委任契約書とは、その名の通り、財産の管理を委任者に任せることができる契約書のこと。
判断能力があり、財産の管理を行いたいと思っているが、体が不自由で銀行や役所にいけない場合、本人に代わって委任者が銀行や役所などで手続きを行うことが可能となります。他にも、入院や介護関係の手続きも行うことが可能です。
②任意後見契約書
任意後見契約書とは、任意後見契約を行う際に必要となる公正証書のこと。任意後見とは、本人の判断能力がしっかりとある時期に、自分の判断能力がなくなった場合の世話をお願いする人を、あらかじめ決めておく制度です。
この制度で委任された方は、依頼した本人の判断能力がなくなってから、本人の代理としてさまざまな処理を行います。財産管理、金融機関や郵便局、証券会社との取引、定期的な収入の受け取りなどがあります。
③尊厳死宣言書
尊厳死宣言書とは、公正証書によって延命治療を行わない旨を意思表示すること。それによって、過剰な延命治療を拒否することができます。
尊厳死とは、病気が末期状態の患者に対して過剰な延命治療を行わず、人間としての尊厳を保ったまま死を迎えることを指します。植物人間状態の患者に対して適用されることが多くなっています。
尊厳死宣言書は、本人が延命措置の差し控えを宣言し、これを公証人が聴取し、事実実験をしてその結果を公正証書にします。現在では、遺言書と一緒に作成する方が増加しているようです。
④遺言書
遺言書とは、自分の死後、財産をどう配分するかを残された相続人に伝えるものです。法定相続よりも強い効力を持っているのが特徴です。
遺言者で財産にかかわる部分では、相続人となる予定の人の廃除、配分の指定、遺産分割方法の指定と分割の禁止などがあり、非常に強い効力を持っていることが分かります。
遺言書がなく、相続で揉めるケースが後を絶ちません。非常に効力の強い遺言書があれば、相続人はそれに従うしかないので揉めごとも起こらないでしょう。財産が少ない場合でも揉めごとは起こる為、遺言書を書いておいた方がいいでしょう。
⑤死後事務委任契約書
死後事務委任契約書は、その名の通り、死後事務委任契約を行ったことを証明する公正証書のこと。死後事務委任契約は、先述したように、亡くなったあとの処理を委任することを指します。処理の内容としては、葬儀や自宅の片付け、公共料金の支払いや整理などがあります。
身寄りのない一人暮らしの高齢者の場合、家族に依頼することができないため、死後事務委任契約書を作成して委任を行う必要性があります。契約書を作成するには、まず委任する範囲を決定します。葬儀から自宅の片付けなど、どこからどこまでを委任するかを決めていきます。
契約書は公正証書で作成するのが無難です。公正証書であれば、本人の明確な意思や委任された方との関係がはっきりとするので、相続人とのトラブルも少なく、公的機関での手続きがスムーズに行われます。
注意!生前契約をしていても、希望していた葬儀が行えない場合とは?
生前契約で葬儀の契約をしていたとしても、長年時が経つにつれて、契約内容が変更となっていることもあり得ます。
時間が経てば、葬儀にかかる費用や物価など、契約が当時とはかけ離れたものとなっている可能性も十分にあり得ます。そうなると、思い描いていた葬儀にはならず、かなり規模を縮小したものとなることも。
契約した内容の更新や、見直しなどができるかを確認しておくと良いでしょう。
今回ご紹介した生前契約は、身寄りがない方やご家族に迷惑を掛けたくないという想いから、注目されています。元気なうちに葬儀を契約しておくことで、自身の死後に金銭的・精神的負担をご家族に掛けたくない方にもおすすめです。是非取り入れてみてはいかがでしょうか。
>>>埼玉県熊谷市の終活シリーズと関連記事はコチラ!
終活クラブファミールの会員登録はコチラ!
WEB無料会員とは?
終活クラブファミールの仮会員制度です。本会員と同じ特典が受けられます。仮会員有効期日までに本入会金をお支払い頂くことで、無期限で特典が受けられるようになります。終活クラブ ファミールへの本入会金お支払い前に、お亡くなりになっても「会員」として特典や割引が適用されます!(葬儀依頼時にWEB無料会員であることをお伝え下さい。)
また、WEB無料会員のキャンセルは無料です。万が一に備えて登録しておくことをお薦めします。
>>>終活クラブファミールの活き活き会員さんのご紹介記事
>>>終活クラブファミールの提携店リスト


 通話無料24時間365日 電話をかける
通話無料24時間365日 電話をかける  ネットで簡単入会
ネットで簡単入会  無料でお届け
資料請求
無料でお届け
資料請求